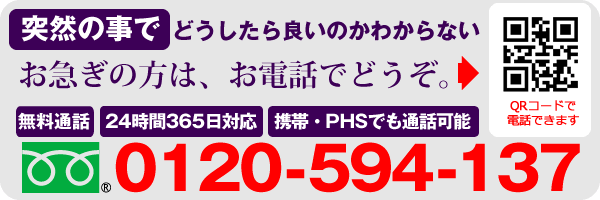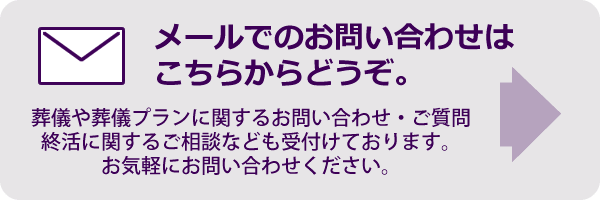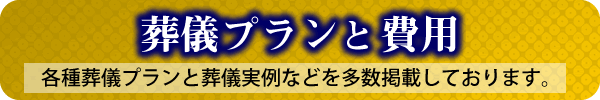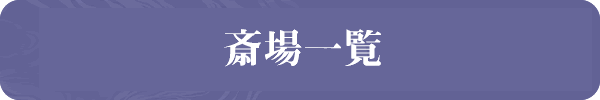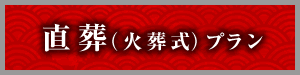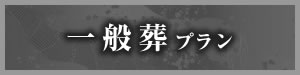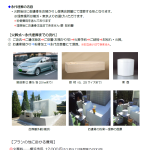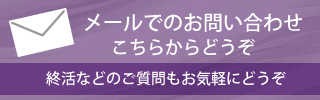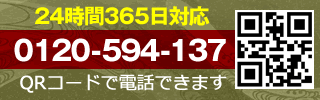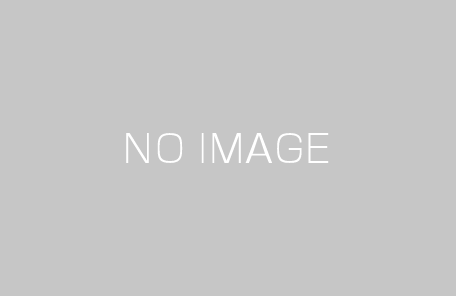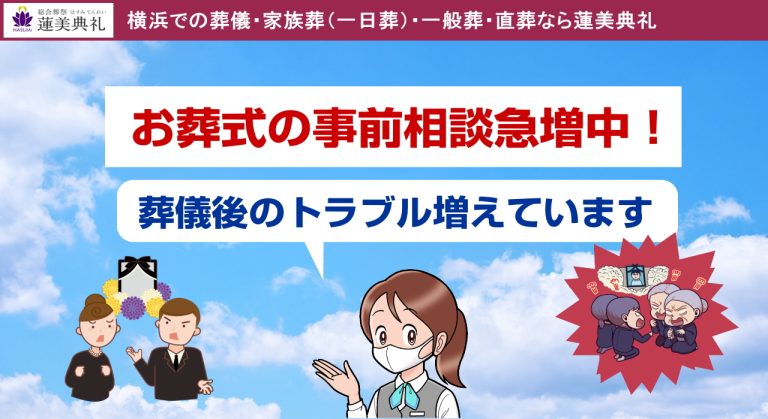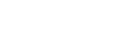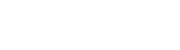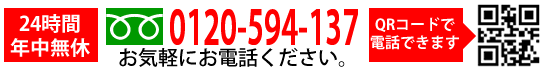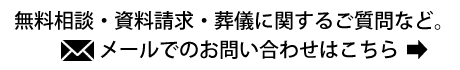はじめに
数珠は、日本の葬儀や通夜など、仏教に基づく様々な儀式で必須とされています。数珠は、古代インドの宗教であるヒンドゥー教から由来しており、その後、仏教に取り入れられ、重要な宗教用具として広く用いられるようになりました。それぞれの数珠の珠には、人間の煩悩を象徴し、これを払う力があるとされています。
しかし、多くの人々が数珠を持ちながら、その起源や意味、使用法について詳しく知らないのが現状です。この文書では、数珠の歴史的背景、基本的な用途、その構成要素とそれぞれの意味について掘り下げていきます。数珠の意味を深く理解することで、通夜や葬儀の際に数珠をより敬虔に、かつ適切に使うことができるようになります。
数珠の起源と基本的な用途
数珠は、通夜や葬儀で必須とされている重要なアイテムです。古代インドのヒンドゥー教で用いられていたもので、お祈りした回数を数える習慣がありました。この習慣は仏教にも受け継がれ、念仏を唱えるときに使用するようになりました。数珠は念仏を唱えるために使用されることから、念仏とも呼ばれます。
数珠の意味
数珠はただ念仏の回数を数えるだけではなく、珠の一つ一つが人間の煩悩を払ってくれるという意味も込められています。珠の数は基本的に108個で、これは人間の煩悩の数と同じです。しかし、現代の数珠は使いやすさを優先し、珠の数が減らされていることがあります。
現代の数珠の変化
108個の珠の半分の54個、または27個など、使いやすさを考慮して数が変更されているケースが多いです。しかし、これらも108に関連した数とされており、煩悩を払う意味合いは変わりません。
数珠のパーツとその意味
正式な数珠は、親珠、主珠、弟子珠など、いくつかのパーツによって構成されており、それぞれに意味があります。例えば、親珠は釈迦如来や阿弥陀如来を表し、主珠は百八尊や百八煩悩を表します。これらのパーツが仏様を意味するもので構成されていることは、数珠の重要な特徴です。
数珠の正しい理解と使用
通夜や葬儀の際に数珠を使用する前に、数珠の意味を正しく理解し、込められた意味をかみしめながら数珠を使うことがお勧めです。
おわりに
数珠は、古代インドの宗教であるヒンドゥー教の影響を受けながら、仏教の宗教用具として発展しました。そのため、数珠を使用することは、ただの形式ではなく、豊かな歴史と深い意味を持つ宗教的な行為です。数珠の各珠は人間の煩悩を象徴し、これを払うという重要な役割を果たします。
通夜や葬儀で数珠を正しく、そして心をこめて使用するには、数珠の意味と起源、さらにその構成要素の意味を理解することが不可欠です。この知識によって、私たちは数珠を通して煩悩を見つめ直し、故人を偲び、自己の精神を浄化することができます。
現代においても、数珠の本質的な意味は変わっていないため、その歴史と意味を理解し、敬虔な心持ちで使用することが重要です。これにより、私たちは仏教の教えに従って、より心静かに、そして意味深く念仏を唱えることができるでしょう。
私たち全てが、数珠の深い意味を理解し、心の底から尊重し、適切に使用することで、その真価を十分に発揮できることを願います。